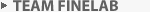



日本のボディビル2団体(JBBF、JPC)の大会で優勝し、さらに世界大会でも優勝をしたボディビルダー「上沢尚志」さんをご紹介します。現在は青森県で「キングポートヘルスジム」を主宰しながら、JPC東北大会を運営したりとボディビルの普及に努められています。キングポートヘルス内でもファインラボの商品は非常に人気があり、上沢さんもボディビルダーにだけではなく、健康志向でトレーニングを行っている会員さんにも勧めるほどです。上沢さんから自身のボディビルについてコラムをいただいたので、ご紹介します。

| 名前 | 上沢 尚志 |
|---|---|
| 所属 | キングポートヘルスジム |
| 生年月日 | 1954/03/24 |
| 身長 | 163cm |
| 体重 | OFF:85kg ON:70〜75kg |
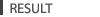
| 1989年 | IFBBミスターユニバース出場、ABBFアジア選手権大会バンダム級準優勝、JBBFクラス別バンダム級1位 |
|---|---|
| 1991年 | IFBBミスターユニバース出場、ABBFアジア選手権大会バンダム級準優勝、JBBFクラス別バンダム級1位 |
| 1995年 | JPCナショナルズ優勝 |
| 1996年 | JPCナショナルズ優勝 |
| 1997年 | JPCナショナルズ優勝 |
| 1998年 | マッスルマニアワールドライト級優勝 |

私とボディービルとの出会いは、25歳のときに、当時私は自衛隊を退職し一般企業で働いていて、そこの職場の先輩に誘われて公共の体育館のウェイトトレーニングセンターを見学に行ったことでした。そこの施設は日本の公共施設にウェイトトレーニングが導入される草分け的なところだったということでして、日本各地から見学にこられていたようでした。私も初めて見たときは驚きました。施設の広さが300坪以上はあり、そこに鉄工所で作ったような器具類がずらっと並んでありまして、ベンチプレス台が10台ぐらい、スクワット台が3台、ラットマシンが4台、ダンベル、バーベル類等がありました。ラットマシンは太い鉄骨柱に溶接して作ったもので、殆んどが手作りでした。そしてこの施設にはじめて入り見たものは、腕の太いデカイ連中が黙々と声を張り上げてトレーニングしている光景でした。しばらくはそのような連中の側には近づけず、施設の片隅のほうでちょろちょろやっていました。私は子供の頃から相撲が好きで、小学校の頃にはよく相撲をとって遊んでいました。大人になっても趣味として続けてきましたので、四股踏み、腕立て伏せ等はやっていまして、下半身に関しては、この四股ふみが大変良かったのではと思っています。ですから当時のトレーニングはあくまでも相撲のための筋トレで、トレーニングも見よう見まねでやってました。また、サンドバッグめがけて立会いの練習をしたり、頭での「ぶちかまし」をしたりしていました。ですからボディービルダー的なトレーニングはしていませんでした。それにボディービル的な体にはあまり興味がなくスポーツをやって自然にできたからだが好きでした。
そうこうしているある年、先輩がボディービルの大会があるから見にいこうと誘われて見に行きました。そこにはトレーニングセンターで見かける選手も何人か出場していてました。ところがその人達が普段トレーニングセンターで見る体とは違い、ステージ上での体の大きさというか、美しさというか、ものすごく大きく輝いて見えたんですね。そこで、このボディービルというものに興味が増し、深まり、体作りの楽しさを感じるようになりました。そして1987年33歳で青森県大会に初出場となったわけです。その大会では初出場ながら3位となりました。これには自分自身信じられないくらい驚きました。何しろそれまでの人生の中で何かで賞を頂くなどという事には全く無縁だったですからね。それはもう衝撃的な出来事でした。特にボディービルという夢にも思っていなかった世界のことでしたから強くそれを感じました。その後は自分の人生観が大変わりするような日々が続き、夢の中にいるのではと思うような出来事の連続でした。その年は東北大会にも出場しまして、成績は7位でした。この7位というのは青森県選手としては10年ぶりの出来事だったということでした。翌年は現在のジャパンオープンの前身のミスターアポロ大会に出場しました。満足に基本ポーズも知らない状態でしたが、これまたびっくりの5位という成績をとる事ができました。そして、さらにボディービル熱が増すとともに自分自身の将来、人生への希望というか自信というか、そのようなものを感じるようになってきました。このようにボディービルをはじめたことにより自分の行き方さえも変えさせた「ボディービル」は、私に取っては命の救い主といっても過言ではないと思っています。人の一生には一度や二度の転機というものがあると思いますが、私にとってはこの頃がそれだったのかもしれません。すでに30歳も半ばになり自分の人生の方向性を決定しなければならない時期でもあり、そういった意味でもその頃の日々の生活は後戻りできないという思いから、職業ボディービルダーを意識しボディービルに生活の全てを注ぎ込んでいました。人生の崖っぷち、相撲でいう土俵際でしたから。
その後の大会出場に於いては、JBBF主催のジャパンオープン大会準優勝、全日本クラス別大会バンタム級優勝、アジア大会バンタム級準優勝2回、そして、1995年舞台をJPCに移し1995年〜1998年まで優勝し、マッスルマニアワールド大会ライト級で優勝という結果を残す事ができました。現在ミスターオリンピアの王者ロニーコールマンは1991年のミスターユニバース大会にヘビー級で出場していてパンプアップルームで見かけたことを思い出しています。その時は、まさかあれほどまでマンモス化するとは想像もつきませんでした。当時の私のサプリメントはプロテインとビタミン剤を少しとるくらいでした。そのためか調整を進めていくうえで体調を崩す事が多くありました。今ではサプリメントの重要性を痛感しています。サプリメントはコンディションを保つ上で欠かせないもので、自分に欠乏しているものは何かという事を的確に把握する必要があります。そのためには専門家のアドバイスを受け知識を豊富にする必要もあります。
トレーニングはごくごく基本的な種目を行っています。まず、ウォーミングアップ2〜3セット終了後3セットぐらいかけてMAXの90%程度まで重量を増やしていき、そこから最高回数4〜5回の重量を5〜6セットかけてダウン方式で進めていきます。インターバルは1分程度ですが場合によっては30秒程度の場合もあります。その他、ディセンディング方式、レストポーズ方式等ももちいます。基本的には一人で行いますが種目によっては補助者をつける場合もあります。減量調整は有酸素運動を多用しています。固定式バイク、ランニング、階段登り、ヒンズースクワット等・・・。しかし、できればあまり有酸素運動はせずに調整したいのですがなかなかできまずじまいというところです。
オフの食事とオンの食事はかなり違ってきます。オフにはビール等アルコール類もかなり飲みますのでオンになればそのアルコール類を絶ちます。それだけでもかなりのカロリーを制限できます。基本的にはオフ時は何でも食べますので、体脂肪もかなり付いています。オンの食事は鳥胸肉、ささみ、マグロの赤身等。炭水化物は玄米、白米、麺類など、また複合炭水化物はサツマイモなども食べます。その他の炭水化物摂取日と摂取しない日などを設け、体がその食事になれないよう気をつけます。1993年に地元青森にトレーニングジム「キングポートヘルスジム」を開業し12年になります。今は日本どこでもそのようなのですが、特に地方になりますと個人の小さいジムなどは経営が本当に大変です。最近はジム内も高齢化になりつつありまして、中年・後年の元気づくりの場として定着しつつあります。また、2000年にはJPC青森県フィジーク委員会を立上げ、委員長として青森県大会、東北、北海道大会を開催しています。これもボディビル大会を通じてボディビルの普及活動の一つとしての役割を担っています。さらに2005年はJPC東に本大会も開催する事となりました。2005年9月25日青森県八戸市八戸市公開同文化ホールにて、一般、及び40歳以上マスターズの2部門で開催されます。現在は1998年のマッスルマニアワールドを最後に7年間ステージには立っていません。その一番の理由は家族の柱としてやらなければならないことの多さによる満足のいくワークアウトができないというところが本音です。そのためこれまではサプリメント等の摂取も疎かでしたが、昨年50歳に突入したということから少しずつトレーニングとサプリメントを強化し新たな目標を見つけチャレンジ精神を持ち続けたいものと思っています。
有名なプロレスラー、カールゴッチの言葉に「技術は人が教えてくれるが ガッツは誰も教えてくれない。自分で手に入れなければならない。それこそが一番重要で、一番大切なことだ。自分に嘘をつくな、ごまかすな、途中でやめるな死ぬまで学び続けなさい。もし学びきったと思ったら お前の命はそこで終わりだ。」という言葉あります。全くこの通りだと私は思っています。自分をさびさせないためにも全国のボディビル道を歩んでおられる皆さん、ボディビルはこれからの世の中に絶対必要になります。ぜひ常に磨き続けたいものです。皆様のご検討をお祈り申し上げます。私が青森で主宰している「キングポートヘルスジム」でもファイン・ラボのサプリメントは大変好評です。ピュアアイソレートはおいしさだけでなくその質の良さは一昔前のプロテインにはありえませんでした。今後もファインラボからのサプリメントには注目しています。最後にこのような機会与えてくださったファイン・ラボの鈴木さんをはじめスタッフの皆さんに心より感謝申し上げます。有難うございました。